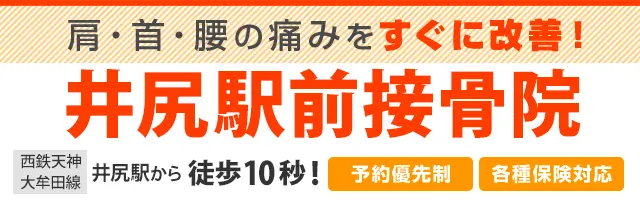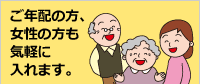肉離れ

こんなお悩みはありませんか?

皆さんこんにちは、井尻駅前接骨院です。
皆さんはこのようなお悩みはありませんか?
よく足などの筋肉が攣りやすい
筋肉痛が取れにくい
攣ったような痛みが2週間以上続く方
スポーツ時に痛みが出やすい
ストレッチの際に痛みを伴いやすい方
上記の様なお悩みを抱えている方は少なくないと思います。
この様な症状を【肉離れ】と言われております。【肉離れ】はスポーツで起こるものだけでなく、日常生活でも多く発生する症状の1つになります。
肉離れで知っておくべきこと

【肉離れ】自体は一般的には【急性症状】と言われる症状になります。
主に【肉離れ】が発生しやすい部位があります。それが【ふくらはぎ】です。【ふくらはぎ】には大きな筋肉が多く付着しており、そのためスポーツ動作で瞬発的な動きや、日常生活の中でも急に動かすことで痛みを発生させてしまうことがあります。
また、季節的な要因もあると思われますが、冬場や夏場などで【肉離れ】の重傷度が変わることがあります。特に冬場では筋肉の結合具合が変化しやすく、回復までにかなりの期間を要することもあります。
スポーツで多く発生するケースとしては、コンタクトスポーツが挙げられます。
症状の現れ方は?

【肉離れ】の症状として、筋繊維の断裂による痛みが現れます。損傷の多くは、瞬発的に筋繊維にストレスが加わり、筋繊維自体がその衝撃に耐えられず、断裂してしまうことで【肉離れ】が発生します。
症状の現れ方としては、初めに軽い筋肉痛のような痛みが現れ、その後、痛みの度合いが変化せずに進行することがあります。痛みの程度によっては、歩行に支障をきたすこともあります。
【肉離れ】には損傷の度合いによって3つの分類があり、一番重い症状では、損傷箇所に陥凹が触れることもあります。
その他の原因は?

【肉離れ】のその他の症状として、筋繊維の瞬発的な断裂だけでなく、日常的な動きでも筋損傷が起こるため、スポーツだけで発生するわけではありません。皆さんも聞いたことがある【ぎっくり背中】も、一種の【肉離れ】の一つといえます。
また、加齢により筋繊維の柔軟性が低下し、筋繊維が断裂することもあります。そのため、【肉離れ】はスポーツだけでなく、日常生活動作によっても発生することが多いです。
多くの方が、趣味で運動をしている方に発生しやすいと認識されているかもしれませんが、夜に足がつってそのままにしておくことで【肉離れ】になるケースもあります。
肉離れを放置するとどうなる?

【肉離れ】を放置してしまうことで、多く発生するのが筋繊維に【硬結部位】ができてしまうことです。【硬結部位】とは、筋繊維が断裂した際に再結合する過程で、【瘢痕組織】という組織が形成されることを指します。
この【瘢痕組織】は血流が乏しく、筋繊維の中で硬い組織となり、【硬結部位】として体表面で触れることができるようになります。一般的に言うと、筋肉の中でゴリゴリとした感触がある箇所が【硬結部位】と言われています。
ただし、すべてが必ずしも上記のような状態になるわけではありません。組織の変化により【瘢痕組織】は再度【肉離れ】を引き起こしやすくなるため、アプローチする際には特に注意が必要です。
当院の施術方法について

当院では【肉離れ】に対する施術方法は時期によって変化します。
受傷直後であれば、患部に対してRICE処置を行い、まず患部の安静と筋組織の再結合を目的に施術を行います。その後、ある程度歩くことや受傷した患部に痛みが出ていない場合には、患部を含めた【筋膜ストレッチ】や【足の極み】などを行い、患部の耐久度や血流循環を再度促進し、立位時や運動時に痛みが出にくい状態に戻していきます。
上記でも述べたように【肉離れ】は時期によってアプローチする施術が変化します。特に受傷直後の対応が長期のリハビリに影響を与えることがあります。そのため、最初期の対応で患部の癒合が良くなるか悪くなるかが変わることがあります。RICE処置を行うことで筋繊維の断裂部位を圧迫し固定し、筋繊維の癒合が早くなることが期待できます。
改善していく上でのポイント

【肉離れ】自体を軽減していくためには、上記でも述べたように最初期の対応が大きく影響します。
競技をされている方の中には、早く復帰したいという気持ちがあるかもしれませんが、【肉離れ】は対処しやすい怪我です。焦ってしまうと、受傷部位が完治していない状態で競技復帰してしまい、体に大きな影響を与えることがあります。
また、時期によってリハビリや施術のアプローチが変化してくるのも、この症状の特徴です。
リハビリも重要ですが、まずはご自身のお身体の柔軟性がどの程度あるのかを理解したうえで、競技を行ったり、日常生活を送っていただきたいと思います。
監修

井尻駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:北海道札幌市
趣味・特技:野球観戦、サウナ、居酒屋巡り